仙腸関節塾2days 第8期【in東京】 参加者募集中!(早期割引枠残り4席)
H30年11月3日,4日開催
おなじみ甲府市の岩松先生(栞 鍼灸整骨院)の動画に「脊柱側屈における左右非対称性」がよく表れたものがありましたので、動画をお借りして側屈動作をちょっとおさらいしましょう。
この動画は吉岡メソッドの施術例ではありません。
側屈のセルフエクササイズについて指導された際に撮影されたものだそうです。
側屈と一口に言ってもいくつかのパターンがあり、それぞれのパターンは主に「荷重」によってコントロールされます。
大きく分けると左荷重の左屈、右荷重の左屈、左荷重の右屈、右荷重の右屈となり、そこに利き足軸足の機能的な非対称性が関わってきます。
まずは一度動画をご覧いただき、側屈の様子を観察してみてください(動画の方が分かりやすいです)。
この患者さん、前半は「左屈がしにくい」と感じています。
その際の静止画がこちら↓。
一度目
(右屈)
(左屈)
どちらも閉脚、上肢下垂の状態で側屈。
仮に純粋な側屈が腰椎に起こるとすると、右屈時には椎間板の左がオープンに、左屈時には右がオープンになります。
腰椎はそれぞれ左凸、右凸の弧を描きながら、荷重を下肢へと伝えます。
上の動作では確かに右屈の方がスムーズで、左屈は上部腰椎でやや窮屈そうに見えます。
荷重は動画で見るとどちらも側屈と同側に向かう傾向があるようです。
二度目
(右屈)
(左屈)
今度はやや開脚、上肢挙上です。
これも動画の方が見やすいですが、今回は側屈と反対側へ荷重が向かいます。
つまり先程とは逆。
側屈は側方への大きな重心移動を伴いますので、側屈と同側への荷重負荷はバランスを崩しますから、自然と反対側へと荷重は向かいます。
上肢の挙上と下垂で動作に多少の違い見られるのは、そうした重心バランスと関係しているものと思われます。
こちらの方が自然な側屈で、可動域も増大します。
ここには最初よりはっきりとした非対称性が現れていて、脊柱の側屈には回旋も加わっています。
どちらも腰椎椎体が左へ「回旋しようとしている」のが分かりますか?
つまり右屈では腰椎は凸側へ、左屈では凹側へ回旋しようとしています。
この患者さん、右利きですね。
この動作には右利きの特徴が強く表れています。
仙腸関節塾受講者の皆さん、この動作も「左が前、右が後ろ」の関係性に対応しているのが分かりますか?
基本的には「軸足が前、利き足が後ろ」のポジションで荷重移動とともに脊柱は屈伸をしている、という状態です。
六度目
(右屈)
(左屈)
この方が分かりやすいかな?
最初と同じ閉脚ですが、荷重は反対側です(上肢の挙上も関係していると思います)。
右屈は全体的に左前がオープン、左屈は右やや後方がオープンです。
単純に左屈を大きくしようとするなら、もう少し屈曲方向へ誘導を掛けると可動域は増大すると思います。
右利きの人は自分でやってみると分かります。
さて、ここで重要なのは、同じ側屈でも左右の動作は対称ではない、ということです。
この動作を左右対称に行うためには動作中左右下肢の荷重バランスは均等を保つ必要があり、それは現実的に不可能であるということを、講義でも資料を用いてお伝えしました。
骨盤および脊柱には機能的な左右非対称性があって、その「動きやすさ」は、基本的に左右差を強調する方向にあります。
当然それが行き過ぎた先には、「左右差の拡大」が待っています。
つまり可動域を向上させるということは、「歪み」を拡大させてしまう可能性もあるということです。
必要なのはパフォーマンスの向上なのか? それとも左右差の解消なのか? 明確な目的をもったアプローチが施術者には求められます。
私はすべての動作が左右非対称性であるという前提で観ています。
そしてどのようなセルフエクササイズも、左右差の解消には繋がらないとも思っています。
改善させるのは休息時の無意識と、それを知る施術者の仕事です。
それぞれ非対称な役割を持つ左右の脳と二本の脚で生活している以上、基本的に動作においてその左右差から逃れることはできません。
そして動作解析は、それを知ることで解釈が大きく変わります。
そのためのヒントが仙腸関節に詰まっているということは、いまさら言うまでもありません(笑)。

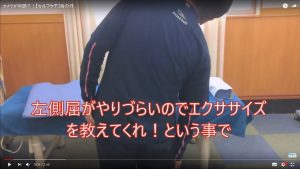






コメント