参加者募集中です。
先日の整動協会さんとのセミナー後、次男が「産後の骨盤矯正」について質問してきました。
簡単に答えておきましたが、良い機会なので、ここでも個人的に思うところを書いてみます。
驚いたことに、このブログ内を検索しても「産後の骨盤矯正」に関する記事はヒットしません。
結構長く続けているのに一度も言及していなかったらしい(笑)。
ちなみにHPにも「産後骨盤矯正」の項目はありませんし、私の方から積極的におすすめする、ということも絶対にありません。
それでも以下を踏まえたうえで「お願いできますか?」といわれたらもちろん、「ハイよろこんで!」と答えます(笑)。
では本題。
もし私が「産後に骨盤矯正は必須ですか?」と尋ねられたら、「いいえ」と答えます。
「必須」とは思っていないからです。
私の親世代では、産後「骨盤矯正に通っていた」なんて人、おそらく皆無でしょう(本当にゼロかどうかはわからないけど)。
その前もそのまた前の世代も同様だと思います。
そもそもそんな言葉自体「聞いたこともない」という方が圧倒的多数のはずです。
私の祖母の世代など、子供を6人も7人も産んだわけです。
産後の骨盤矯正が不可欠であるなら、そんなに産めませんよね。
だって一年置きとかにお産ですよ。
なかには産後の腰痛など不調で悩まれた方もいたでしょうけど、それ以外は特に支障なく生活し、多くは骨盤矯正など受けずに大きなお腹で子育てに追われていたに違いありません。
(先人からの知恵に従い産後しばらく腹帯を巻いていた、くらいはあると思いますが。)
女性の妊娠出産が骨盤への(もちろん骨盤以外にも)大きな負担を要する一大イベントであることは間違いないとは思いますが、それをいちいち他者の手を借りて元に戻さなければならないようでは、人類などとっくの昔に絶滅していたはずです。
産後の骨盤には当然変化は生じているはずですが、放っておいても自然と元通りになるからこそ、これまで絶えることなく命は繋がれてきたのです(二人以上産まないと人口は減っていく)。
「産後の骨盤矯正」があたかも「必須」であり、それをしなければ不調に繋がるかのような喧伝は、集客だけを目的に不安をあおり、産後の女性に要らぬストレスを与えかねないあくどいマーケティング戦略にしか私には見えません。
では「産後の骨盤矯正は不要なのか?」と問われたらどうか。
「基本的には不要」と考えます。
仙腸関節の安定性という意味では、盤石ではないとは思います。
しかし放っておいても勝手に元に戻るものを、わざわざお金と時間を使ってまで戻そうとする必要はありません。
では「産後に骨盤矯正は必要ないのか?」と聞かれた場合はどうか。
これに対しては「必要な時には必要」と答えます。
私は別に「産後だから骨盤矯正をすべき」とは思いません。
産後だろうが産前だろうが、女性だろうが男性だろうが、大人だろうが子供だろうが、必要な時には必要、それだけのことです。
つまり「産後だから」といった特別扱いはなくて、「産後でも」必要なら行う、ということ。
「自覚できる不調があるならそれも考慮すべき」とは真面目に思う。
産後の骨盤は妊娠中から分泌されるホルモンの影響で靭帯が弛緩していますから、妊娠中も含め、たしかに「歪みやすい」状態にあると思います。
でもその歪み方には妊娠中あるいは産後に固有の傾向があるわけではなくて、誰もが持っている機能的非対称性が拡大した状態でしかないと私は考えています。
関節は動くべき方向にしか動けません。
妊娠中だけその動きが変わる、なんてことになったら、仙腸関節の機能を根底から見直さざるを得ないほどの大問題です。
つまり産前でも産後でも、やるべきことは同じ。
私自身は「産後骨盤矯正」なるものをどこかで学んだことがありません。
これだけ仙腸関節を観察し続けていて、興味を惹かれたこともありません。
産後の骨盤矯正が関節の矯正であるなら、産前も産後も関係なく、必ず正しい方法があるはずだ、と思っているだけです。
私は私の仮説に基づいて骨盤矯正を行っています。
仮説なので、もちろんそれが正しいと証明されたものではありません。
でもあらゆる仮説を調べ尽くして、いまのところ一番正解に近そうだと自負しています。
そのうえで、産後の骨盤矯正についてはこのように考えています。
産後にのみ特化した骨盤矯正など思いつかない、と。
ついでに言えば、産前産後、老いも若きも男も女も、それをやらない方が良い、という理由も特に思いつきませんけど(マーケティング戦略?笑)。
「餅は餅屋」という言葉がありますね。
私は誰よりも餅が好きで、餅に詳しい「餅屋」でありたいと常に思っているのです。
それが私の仕事なので。
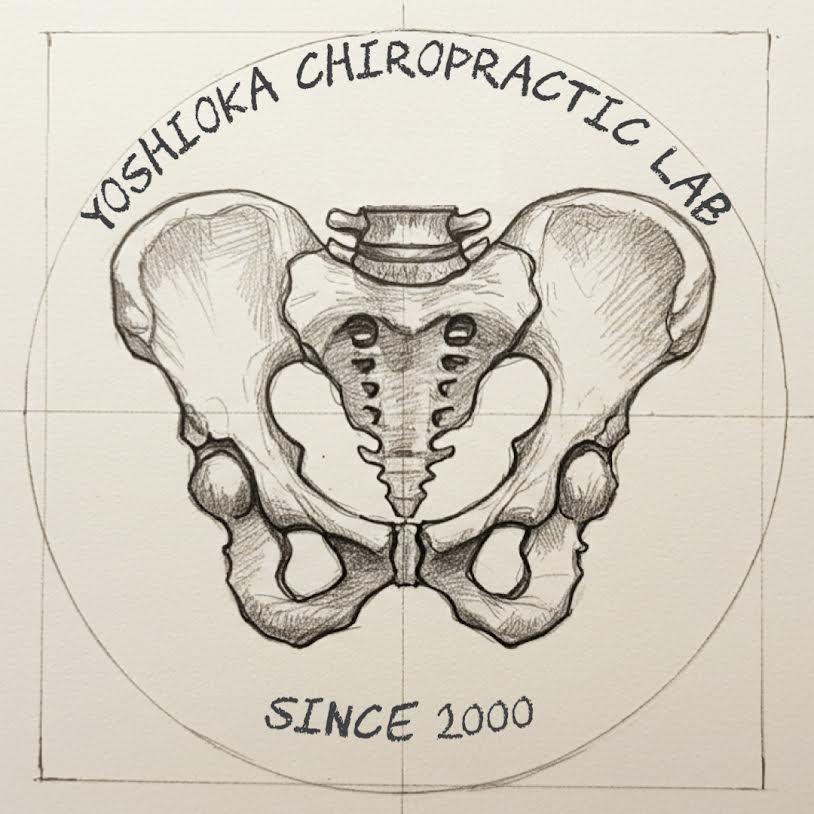

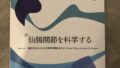
コメント