久しぶりの更新、久しぶりの本の紹介なので、3冊まとめて。
まずは「構造主義科学論の冒険」(池田清彦著 講談社学術文庫)
そして「構造構成主義とは何か ~次世代人間科学の原理」(西條剛央著 北大路書房)
さらに、「科学の剣 哲学の魔法 ―対談 構造主義科学論から構造構成主義への継承」(池田清彦 、西條剛央 著 北大路書房)
3冊とも科学論、科学哲学のお話です。
おすすめです。なんか面白い本はないかなぁと探している最中の方は、とりあえず読んでみてね。
30才を過ぎてから論文など書き始めた僕は、それまで書き方の指導とか訓練とか全くなしに、ぶっつけ本番でA4五十枚ほどの論文を書きました。当然きちんとしたものが出来上がるわけもなく、それを丁寧に修正してくださったのが、同じPAACの大先輩である前田滋先生でした。
それから何の因果か毎年のように論文を書き続けたのですが、その過程で、非常に参考になったのが上の3冊です。論文の書き方の参考、ではなく、科学とは何か、という点で、これらはとても参考になりました。
「科学的に」とか「科学的な」とかいう言葉は気軽に使いますが、「そもそも科学って何?」と考えることはあまりありません。それを考える分野が「科学論」とか「科学哲学」という学問で、ようするに「科学全般を科学(哲学)するメタ理論」とでも言えるでしょうか。
「カイロは科学的な根拠に基づく治療法でウンヌンカンヌン」という言葉に違和感を持っていたこともあり、上記の3冊に書かれていたことは割とすんなり受け入れられました。というより、目からうろこでした。
カイロプラクターはあまり論文を書かないので、科学的とはどういうことか、ということを考える機会もありません。
教科書に書かれている内容は正しい、と無条件に受け入れてしまうピュアな学生も多く、僕が講義であれはおかしい、なんて言った日には、ハトが豆鉄砲みたいな顔でポカーンとされることもしばしばです。
教科書に書いてあることがすべて正しいという思い込みは危険で、それって本当なの?という疑問を常に持ちながら学ばないと、成長はありません。個人もそう、業界もそう。
何が言いたいのかというと、要は「自分で考えなさい」ということ。
科学とはどういうことか? 科学的とはどういうことか? 教科書に書かれていることは本当に信用に値する内容なのか?
カイロプラクターも、これからはこうした視点で物事を見極めていかないと、この先生き残れる保証はありませんし、胡散臭い連中に簡単に騙されます。
騙されて恥をかくのはその本人。迷惑をこうむるのは患者さんです。
なるべく他人には迷惑をかけないようにしましょう!

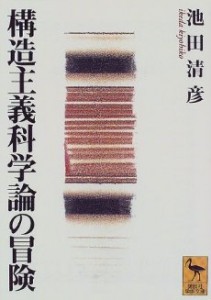
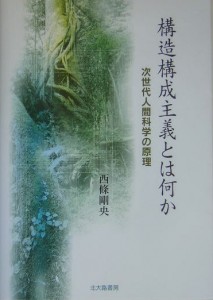
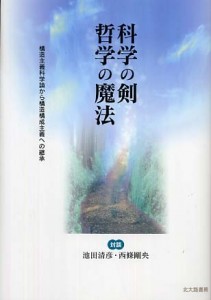

コメント